
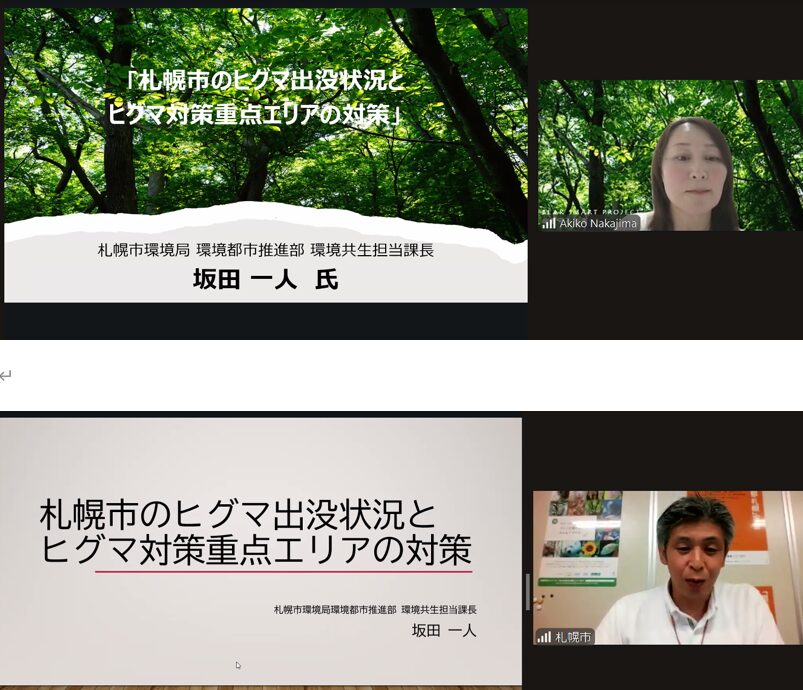
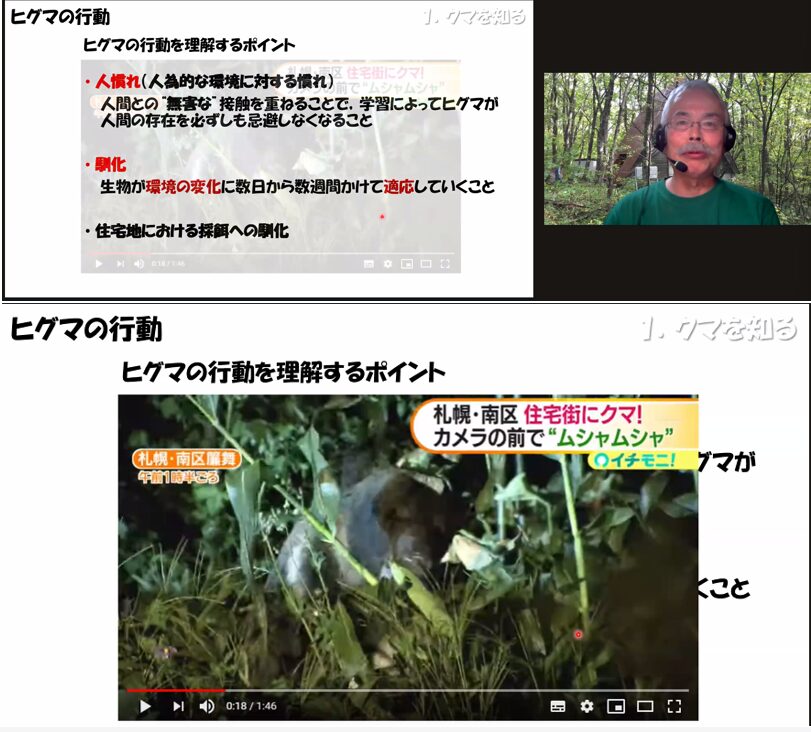
「Bear Smart Project」ヒグマクラス(オンライン事前学習)「命を守る知恵~ヒグマとの距離をどう保つか」
9月3日 Online
【Report】ヒグマクラス
9月3日にオンラインヒグマ学習「命を守る知恵~ヒグマとの距離をどう保つか」を開催しました。学習は「講義1時間+質疑応答1時間」の構成で、参加者の皆さまが日々の生活に活かせる知恵を得られる、充実した時間となりました。
まず、札幌市環境局の坂田様から、市内でのヒグマ出没状況や具体的な予防対策についてご説明いただきました。
今年は実りが少ないため、人家周辺での出没を防ぐには、家庭菜園や果物の管理、電気柵の設置、落ちた果物・生ごみの片付けなど、身近にできる対策が欠かせないとのことでした。札幌市には電気柵購入補助制度があり、申込期限は9月19日までです。また、重点エリアでの「トレンベア」の設置、さらに改正された鳥獣保護管理法のポイントについても解説がありました。
続いて、北海道総合研究機構フェローの間野様からは、「事故を防ぐための行動と心構え」として①ヒグマの行動理解、②福島町事故の教訓、③ゴミがもたらすリスク(餌付け)、④仲間を守る知恵についてお話しいただきました。
特に「人間にとって問題となる行動をクマに学習させないこと」の大切さが強調されました。ヒグマは経験から学習するため、人間と接点を持った際の私たちヒト側の行動が大きな影響を与えます。たとえば、クマ鈴は正しく使えば人を避ける効果がありますが、餌と結びつけられてしまう(食べ物の放置、餌付け)と逆に音で寄ってくる危険があります。また、2001年の北海道ヒグマ管理計画にはすでに「生ごみ管理」の重要性が記されていましたが、実行が伴わなかったため対策が十分に進まなかったことも紹介されました。知識や計画があっても、実際の行動につながらなければ成果には結びつかない――その重みを改めて学ぶことができました。
さらに、公益財団法人知床財団の伊集院様からは、ヒグマ生息地に入る際の注意喚起をいただきました。ゴミ(餌付けとなるもの)を正しく管理すれば軋轢は防げること、山に入る前には必ず情報と知識を得ることの重要性を強調されました。特に、トレイルランニングや自転車は危険であること、クマスプレーの携行と正しく使用できる知識と練習も重要であること、複数人での行動、悪天候時の入山を避けることなど、具体的で実践的な行動の指針を示してくださいました。
ヒグマについて正しく知ること・学ぶこと・行動することは、北海道に住む私たちにとって特別なことではなく、日常に必要なことです。誤った情報や行動は、自分だけでなく周囲の人の命をも危険にさらします。ぜひ一人ひとりが「自分ごと」として学びを生活に取り入れ、地域の知恵として共有していくことが大切です。
今回の学習を通じて、私たちは「命を守るためにヒグマとどう距離を保つか」を深く考えることができました。自分を守ることは、他の人を守ることにもつながります。これからも知恵を共有し、事故のない環境づくりを進めていきたいと思います。
この度ご協力いただきました坂田様、間野様、伊集院様、そしてご参加いただいた皆さま、TSUNAGUのメンバーに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。